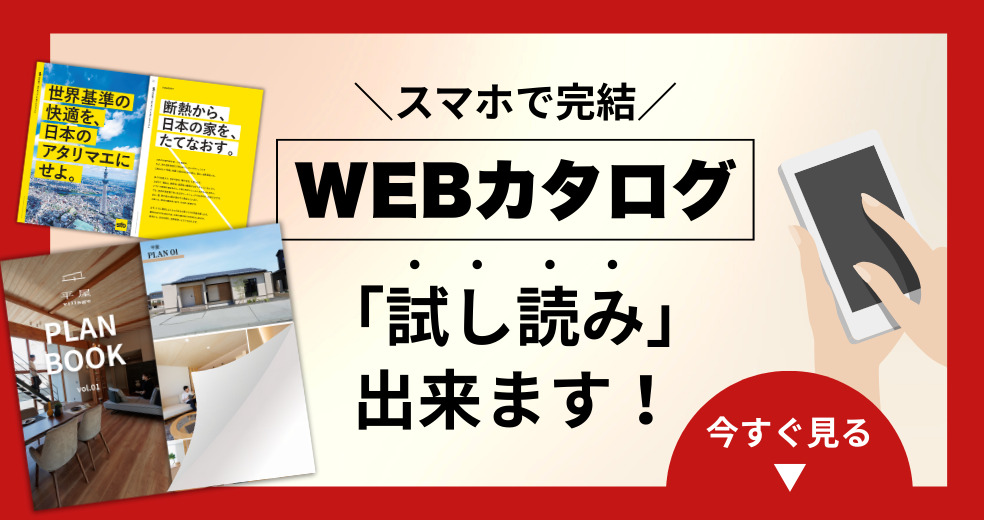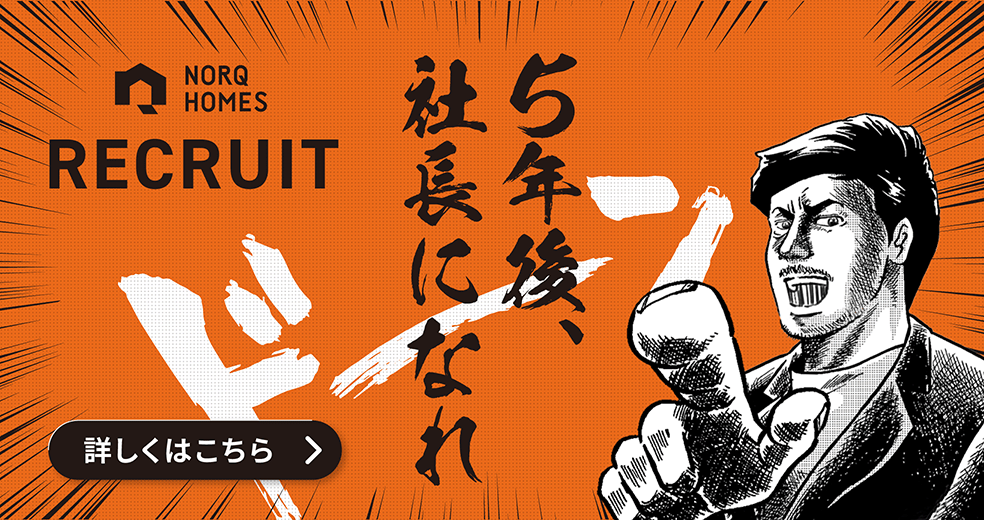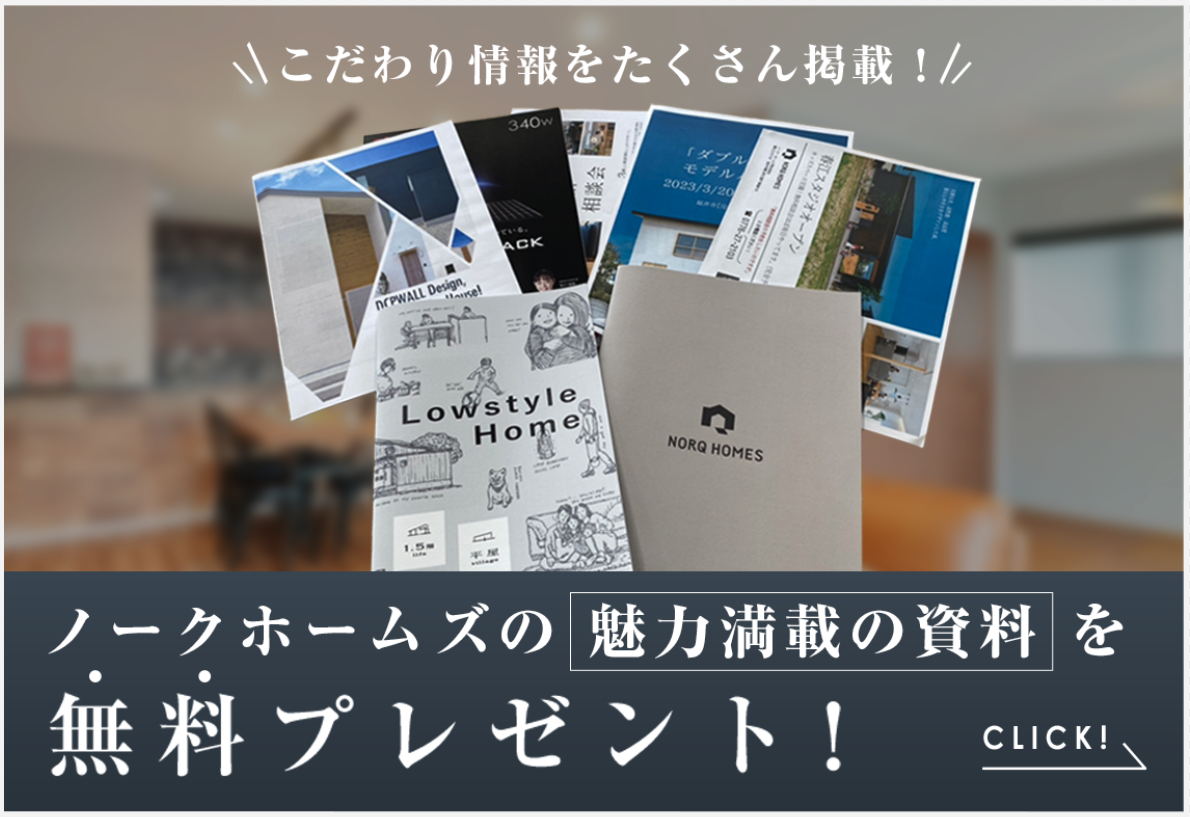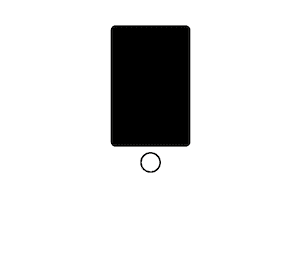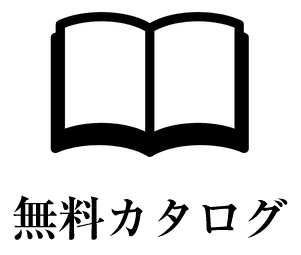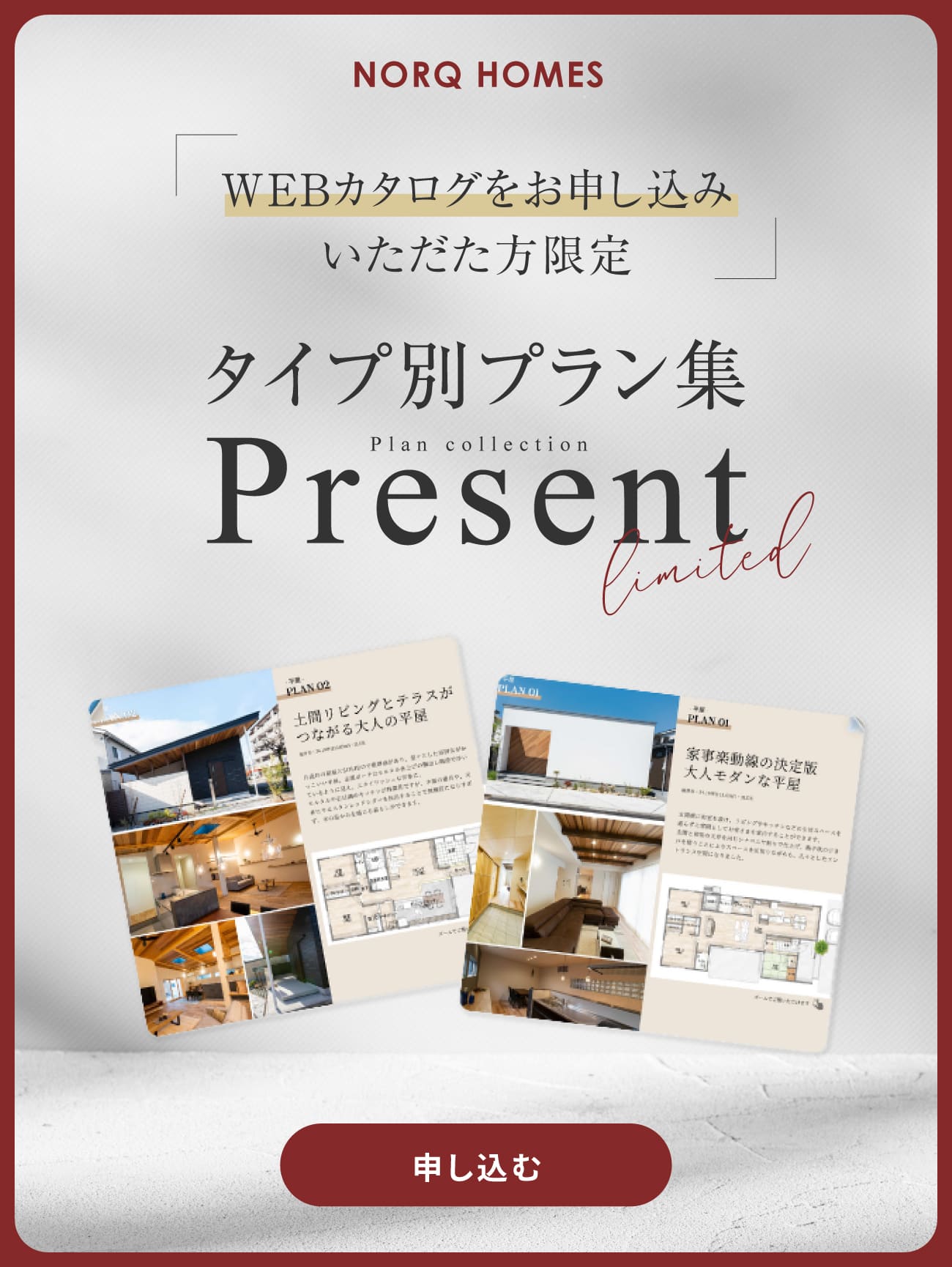親の土地に家を建てる際の住宅ローン利用条件|生前贈与などのメリット・デメリット、相続トラブル回避法も解説

親の土地に家を建てる場合でも住宅ローンを利用可能ですが、ご自身名義の土地に家を建てる場合とは、利用条件が違います。
また、親の土地に家を建てる手続きは「生前贈与をするか」「無償・有償どちらで使うか」などのパターンがあり、各手続きのメリット・デメリットを把握したうえで、ご家族にとって負担の少ない選択を検討する必要があります。
今回は福井・石川で多くのご家族の家づくりをサポートしてきた『ノークホームズ』が、親の土地にスムーズに家を建てるために必要な情報を、わかりやすく解説します。
土地取得費用を抑えて理想のマイホームを完成させるために、ぜひ最後までごらんください。
※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。
目次
親名義の土地に家を建てる際の住宅ローン利用条件、住宅ローンを返済できない場合の影響

親の土地に家を建てる場合、「住宅ローンは建物の建築費用のみを支払うために利用する」というケースが多いのではないでしょうか。
建物の建築費用のみを借り入れする場合でも、多くの金融機関は「親が土地の物上保証人or連帯債務者になること」を借り入れ条件としています。
【物上保証人とは】
「物上保証人」を簡単にいうと「担保提供者」のことで、物上保証人である親は、ご自身の土地にお子さまの住宅ローンの抵当権を設定することになります
そのため以下のような場合には、住宅ローンを利用できない可能性があると考えておきましょう。
- 親が抵当権の設定に同意しない
- 親の土地にすでに抵当権が設定されている(親の住宅ローンが残っているなど)
また、住宅ローンの返済が難しくなった場合には、以下のような状況になる可能性があります。
- 土地の名義が親であっても、土地を失う可能性がある
- 住宅ローン返済中に親が土地の名義変更・売却などをする場合は、金融機関への相談が必要で手続きも煩雑になる
【連帯債務者とは】
連帯債務者は、常に債務全額に対して返済する責任を負っています。
そのため、住宅ローンの返済が難しくなった場合は、親が返済をすることになります。
※「連帯債務者」と似た言葉に「連帯保証人」がありますが、意味が違います。「連帯保証人」については、のちほど「親の土地に家を建てて一緒に住む場合の住宅ローンの借り入れ方法は4パターン」でわかりやすく解説します。
「親名義の土地に家を建てる場合」に金融機関共通で指定していることの多い住宅ローン利用条件を確認してきましたが、親の土地に家を建てる際には、「親名義のまま家を建てる」以外にも手続きの選択肢があります。
そこで次に、親の土地に家を建てる際の手続きのパターン、各手続きのメリット・デメリットを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
福井・石川で親の土地を活用して家を建てることを検討中の方は、ノークホームズへお問い合わせください。
住宅ローンに関する疑問・不安を丁寧に解決しながら、理想の家づくりをサポートいたします。
※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。
親の土地に家を建てる際の手続きは生前贈与など3パターン|各手続きのメリット・デメリット

親の土地に家を建てる際の主な手続きは、以下3パターンです。
- 親に土地を無償・有償で生前贈与してもらって家を建てる
- 親の土地を無償で借りて家を建てる
- 親の土地を有償で借りて家を建てる
それぞれの特徴・具体的な手続きを、わかりやすく解説します。
親に土地を無償・有償で生前贈与してもらって家を建てる
親に土地を無償・有償で生前贈与してもらう主なメリットは、以下のとおりです。
- 土地の取得費用を抑えられるため、無理のない資金計画を組み立てやすい
- 土地の名義がご自身になるため、ご自身の責任の範囲内で住宅ローンを借り入れできる(前述した抵当権・物上保証人などを気にする必要がない)
- 親の財産が減少することで、相続税の納税負担を軽減できる場合がある※
※「親に土地を生前贈与してもらう場合に相続税の納税負担を軽減できるかどうか」については、贈与税の計算方法(相続時精算課税or暦年課税)・土地の価値などに応じて結論が変わります。
そのため、弁護士・税理士等の専門家へ、詳細なシミュレーションを依頼することをおすすめします。
親に土地を無償・有償で生前贈与してもらう場合には、土地の価値に応じて贈与税・不動産取得税が発生することに注意が必要です。
また、親の財産を相続する方(ご兄弟など)が他にもいらっしゃる場合、無断での生前贈与によって相続トラブルが発生するケースがあるため、生前贈与を決定する前にご家族間でよく話し合うことをおすすめします。
子の手続き
親に土地を無償・有償で生前贈与してもらう場合の子の手続きは、以下のとおりです。
- 弁護士・税理士等の専門家へ相談して贈与税の計算方法(相続時精算課税or暦年課税)を決める
- 贈与税の計算方法に応じて、確定申告・届出書提出
- 贈与税・不動産取得税が発生する場合は納税する
- 贈与内容を証明する書類(例:贈与契約書)を作成し、ご家族間で内容を共有したうえで、必要であれば承認印も取得しておく
- 土地の名義変更の登記手続き
- 土地の一部を生前贈与する場合は、分筆の手続き(境界の確定、登記など)
親の手続き
親も、子に土地を無償・有償で生前贈与するにあたって以下のような手続きが必要です。
弁護士等の専門家に相談しながら、不備なく手続きを進めましょう。
- 子と共同で贈与内容を証明する書類を作成
- 必要であれば、土地以外の財産分与の内容について遺言状などを作成
親の土地を無償で借りて家を建てる

親の土地を無償で借りる場合、法律上の取り扱いは「使用貸借」となります。
使用貸借で親の土地に家を建てる場合のメリットは、以下のとおりです。
- 無償or固定資産税額以下の額で土地を借りる場合、贈与税の対象とならない
- 土地の取得費用が必要ないため、無理のない資金計画を組み立てやすい
過去には「無償での使用貸借=借りた側が借地権相当分の利益を得ている」とみなされて贈与税の対象となっていましたが、2021年に国税長官が出した通達により、贈与税が発生しないことが周知されました。
〈参考〉国税庁ホームページ『使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて』
親の田んぼに家を建てる場合の手続きを、こちらの記事で確認できます。
>田んぼ・畑だった土地に家を建てるメリット・デメリット、費用、手続き、家を建てるまでの期間など簡単解説
ただし、使用貸借を選択する場合にはデメリットもあるため、確認しておきましょう。
- 土地に金融機関の抵当権設定が必要で、親が抵当権設定に同意しない場合は、担保ありの住宅ローンを利用できない
- 将来親が土地を売却などで手放すことになった場合、新たな土地所有者が使用貸借を継続してくれるとは限らない
- 将来、親から土地を贈与・相続で取得する際に、土地の評価額(贈与税・相続税の計算の元となる額)が高い※
※親が土地活用でアパート経営をしていて土地を完全に自由に使えない場合などは、贈与税・相続税計算時に土地の評価額を減額できます。
〈参考〉国税庁ホームページ『使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて』
子の手続き
親の土地を無償で借りて家を建てる場合の子の手続きは、以下のとおりです。
- 使用貸借の内容を証明する書類(例:使用貸借契約書)を、親と共同で作成
- 住宅ローン借り入れ時に、抵当権設定登記などが必要
親の手続き
親の財産を相続する方(ご兄弟など)が他にもいらっしゃる場合、無断で土地の使用貸借を実施すると、ご家族の関係性に問題が起きるケースがあります。
そのため、使用貸借を決定する前に、ご家族間でよく話し合うことをおすすめします。
親の土地を有償で借りて家を建てる

権利金・地代を支払って親の土地に家を建てる場合は、市場の売買価格よりも抑えた額で土地を使用できる可能性があり、通常は贈与税の対象にもならない点がメリットです。
ただし、以下のデメリットがあることを念頭に置いておきましょう。
- 親が受け取った権利金・地代は所得税の対象となり、親が確定申告をする必要がある(納税額が発生することもある)
- 土地の使用期間が長いほど総支払額が多くなる
- 土地の名義は親のままなので、住宅ローン借り入れ時には抵当権設定等が必要
- 権利金が通常の土地の価値よりも著しく低い額の場合、将来土地を贈与・相続で取得する場合に、土地の評価額(贈与税・相続税の計算の元となる額)が高い
〈参考〉国税庁ホームページ『相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて』
子の手続き
親の土地を有償で借りて家を建てる場合の子の手続きは、以下のとおりです。
- 借地権の設定契約書を作成し、登記をする
- 賃貸借契約書を作成し、親と契約を結ぶ
- 住宅ローン借り入れ時に、抵当権設定登記をする
親の手続き
子に土地を有償で貸す場合、親は毎年所得税の確定申告が必要です。(納税額が発生することもあります)
また、親の財産を相続する方(ご兄弟など)が他にもいらっしゃる場合、土地の使用が原因でご家族の関係性に問題が起きるケースがあります。
そのため、賃貸借を決定する前に、ご家族間でよく話し合うことをおすすめします。
親の土地に家を建てて一緒に住む場合の住宅ローンの借り入れ方法は4パターン

親の土地に家を建てる場合の手続きを確認してきましたが、ここで「親の土地に家を建てて親と一緒に住む場合、住宅ローン返済負担はどのように分担するの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
住宅ローンの借り入れ方法は主に以下4パターンで、借り入れ方法によって返済に対する責任などが変わります。
- 親or子が単独で借り入れ
- 親子ペアローンで借り入れ
- 親子リレーローンで借り入れ
- 収入合算で借り入れ
ご家族の経済状況などに応じて最適な住宅ローンの借り入れ方法を選ぶために、それぞれの特徴を確認しましょう。
親or子が単独で借り入れ
親or子が単独で住宅ローンを借り入れをする場合、基本的には住宅ローンを借り入れした本人のみが返済の責任を負います。
ただし「親名義の土地に家を建てて子が単独で住宅ローンを借り入れる」という選択をして住宅ローンの返済が難しくなった場合は、親にも以下のような責任が発生します。
- 親が物上保証人になる場合:土地の価値の範囲内で住宅ローンの返済を保証
- 親が連帯保証人になる場合:常に住宅ローン全体の返済を保証
親子ペアローンで借り入れ

親子ペアローンとは親・子それぞれが同時に住宅ローンを借り入れる方法で、特徴は以下のとおりです。
- お互いに連帯保証人※となるのが一般的
- 各自がご自身の住宅ローンに対して返済の責任を負い、同時に返済していく
- 各自が団体信用保険に加入できる
- 各自が住宅ローン控除を活用できる
- 住宅ローンを2本契約するため、借り入れ時の手数料などを2本分支払う必要がある
※連帯保証人は、債務者が住宅ローンを返済するのが難しくなった場合のみ返済を保証します。
親子リレーローンで借り入れ
親子リレーローンとは、「親から子へ住宅ローンを引き継ぐ」という条件の住宅ローンで、特徴は以下のとおりです。
- 子が親の連帯債務者(常に住宅ローン返済の責任を負う)となるのが一般的
- 契約当初の主債務者は親で、決まった期間が終了したら子が主債務者となる
- 親or子どちらかが団体信用保険に加入
- 主債務者の期間に住宅ローン控除を活用できる
- 住宅ローン契約は1本なので、借り入れ時の手数料なども1本分
収入合算で借り入れ
収入合算は、合算者の収入を合わせて住宅ローンの審査を受け、1本の住宅ローン契約をします。
特徴は以下のとおりです。
- 収入合算者は、お互いに連帯保証人or連帯債務者になる(金融機関による)
- 収入合算者の一方のみ団体信用保険に加入
- 収入合算者の一方のみ住宅ローン控除を活用できる
- 住宅ローン契約は1本なので、借り入れ時の手数料なども1本分
住宅ローンの借り入れ方法・各借り入れ方法の一般的な特徴を紹介してきましたが、住宅ローンの契約内容は、金融機関によって違います。
ご家族の経済状況、年齢などの条件を長期的に考慮して、各自にとって無理なく住宅ローンを分担できる返済方法を選んでいただけると幸いです。
福井・石川でマイホームを検討中の方は、ノークホームズへお問い合わせください。
家を建てる土地を決める段階・住宅ローンを検討している段階から、ご家族をサポートいたします。
※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。
親の土地に家を建てると相続トラブルの危険性がある|相続トラブル回避法

次に、親の土地に家を建てる場合に、ご家族間の相続トラブルを回避する方法も確認しておきましょう。
親・相続権を持つ方全員が財産分与の内容を話し合いのみで決め、全員が同じレベルで記憶しておくことは難しいですよね。
ご家族間の相続トラブルを回避するために、必要に応じて第三者に介入を依頼し、財産分与の内容を書面にして「記録」「保管」「書面がある旨を相続人に周知」しておくことをおすすめします。
| 書類 | 第三者 | 保管 |
|---|---|---|
| 家族信託 | 公証人 | 「自筆証書遺言書保管制度」で法務局に保管を依頼できる |
| 遺言状 | ||
| 遺産分割協議書 | なし (相続人全員が署名・押印するため、第三者不要) |
相続人全員分の原本を作成し、各自が保管する |
また、相続財産の中で「家を建てた土地の価値」が飛び抜けて高額な場合には、遺言状などの内容によらず、ほかの相続人が「遺留分※」を請求するケースもあります。
【遺留分とは】
兄弟以外の相続人に対して法律上認められている最低限の取り分のことで、親が相続人の1人へ生前贈与した土地も、遺留分請求の対象となります。
親はご自身の生命保険などで遺留分請求に備えることが可能ですが、実際にはご家族の状況に応じて対応する必要があります。
そのため、弁護士などの専門家へ前もって遺留分請求への対応を相談しておくと安心です。
親の土地に家を建てるQ&A

最後に、親の土地に家を建てることを検討している方から、ノークホームズがよくいただく質問・回答を紹介します。
Q.親が実家の住宅ローンを完済していない。自分の名義で住宅ローンを利用して実家を建て替えできる?
A.親が住宅ローンを完済していない場合、ご自身が住宅ローンを利用して実家を建て替えるのは、難しいのが一般的です。
理由は、同じ土地に2本の住宅ローンの第一抵当権設定ができないためです。
選択肢として「親が、住宅ローンを借り換えする(住宅ローン残債に建て替え費用を追加して、新しい住宅ローンを借り入れする)」などの方法がありますが、ご家族の状況に応じて最適な選択が変わります。
まずは施工業者へ家づくりのプランを相談したうえで、必要に応じて金融機関などへの相談も検討しましょう。
こちらの記事で、二世帯住宅の建て替え費用を確認できます。
>二世帯住宅の建て替え費用はどのくらい?タイプ別費用相場とコストを抑えるポイント
Q.住宅ローン返済中に土地名義人の親が自己破産をしたら、家を没収される可能性はある?
A.土地名義人の親が自己破産をした場合の対処は、金融機関によって異なります。
金融機関は家を没収しても住宅ローン残債を全額回収できるとは限らないため、ただちに家を没収される可能性は低いと想定できますが、早めに金融機関へ相談しましょう。
Q.親の信用情報に問題がある場合、自分の住宅ローン審査に影響はある?

A.親を住宅ローンの連帯債務者or連帯保証人とする必要がある場合には、ご自身の住宅ローン審査に影響する可能性があります。
信用情報は個人でも確認できるので、親の信用情報に不安がある場合には、信用情報機関へ「開示請求」をして、情報を確認してみましょう。
Q.親の土地内の実家の隣に家を建てられる?
A.法律上、1筆の土地内に2軒の家を建てることはできません。
実家が建っている親の土地を分筆・分割し、隣に家を建てることは可能です。
- 土地の分筆とは:1筆の土地を2筆に分ける。登記簿上も2筆の土地になる
- 土地の分割とは:土地内を線引きして分ける。登記簿上は1筆の土地
ちなみに、分筆・分割をせずに実家の隣に家を建てたい場合には、土地ごとに定められている「建ぺい率(土地面積に対する建築面積の割合)」「容積率(土地面積に対する延床面積の割合)」の範囲内で以下の選択肢もあります。
- 離れを建築
- 増築
ただし、離れは「キッチン・トイレ・浴室のうち1つが欠けていないと建築が認められない」など、制限がある点に注意が必要です。
福井・石川で親の土地を活用して家を建てることを検討中の方は、ノークホームズへお問い合わせください。
現地調査のうえで、最適なプランを提案いたします。
※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。
Q.親の土地内に未登記の倉庫があるが、家を建てられる?
A.未登記の倉庫の状況に応じて登記をすることで、家を建てられる可能性があります。
ただし倉庫の状況によっては希望通りの建築プランを実現できないケースもあるため、実施するべき手続きなどについて、司法書士・土地家屋調査士といった専門家に相談することをおすすめします。
Q.親の土地に家を建てる場合も住宅ローン控除を活用できる?
A.住宅ローンを利用して家を建てる場合には、住宅ローン控除を活用できます。
ただし住宅ローン控除には所得額・建築面積・省エネ性能などさまざまな適用要件があるため、前もって確認が必要です。
住宅ローン控除の詳しい内容を、こちらの記事で確認できます。
>住宅ローン控除は2025年以降も利用できるか|利用要件、対象となる省エネ基準を解説
まとめ
親の土地に家を建てる場合でも住宅ローンを利用可能ですが、ご自身名義の土地に家を建てる場合とは違う手続きが必要です。
また、土地の取り扱い・住宅ローンの利用方法について複数の選択肢があるため、今回の情報を参考にしてご家族にとってベストな選択を検討していただけると幸いです。