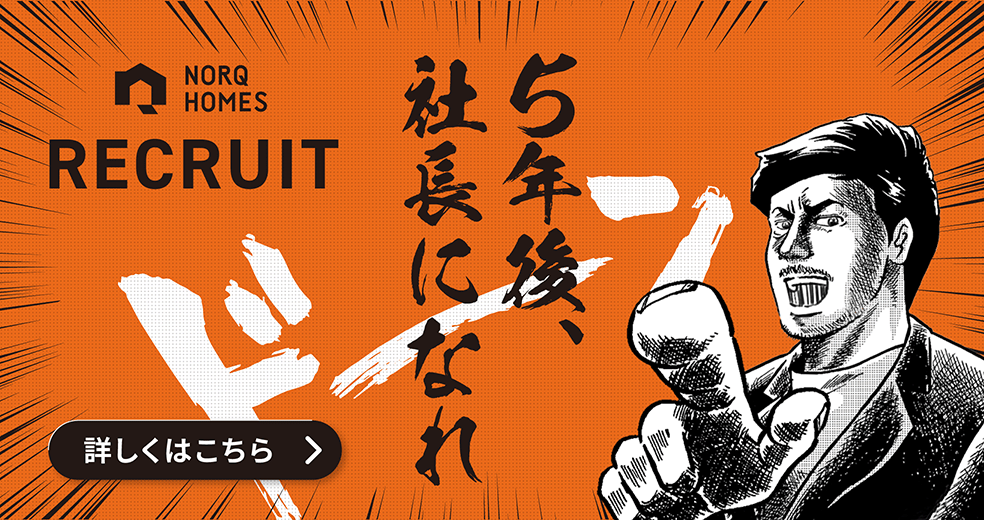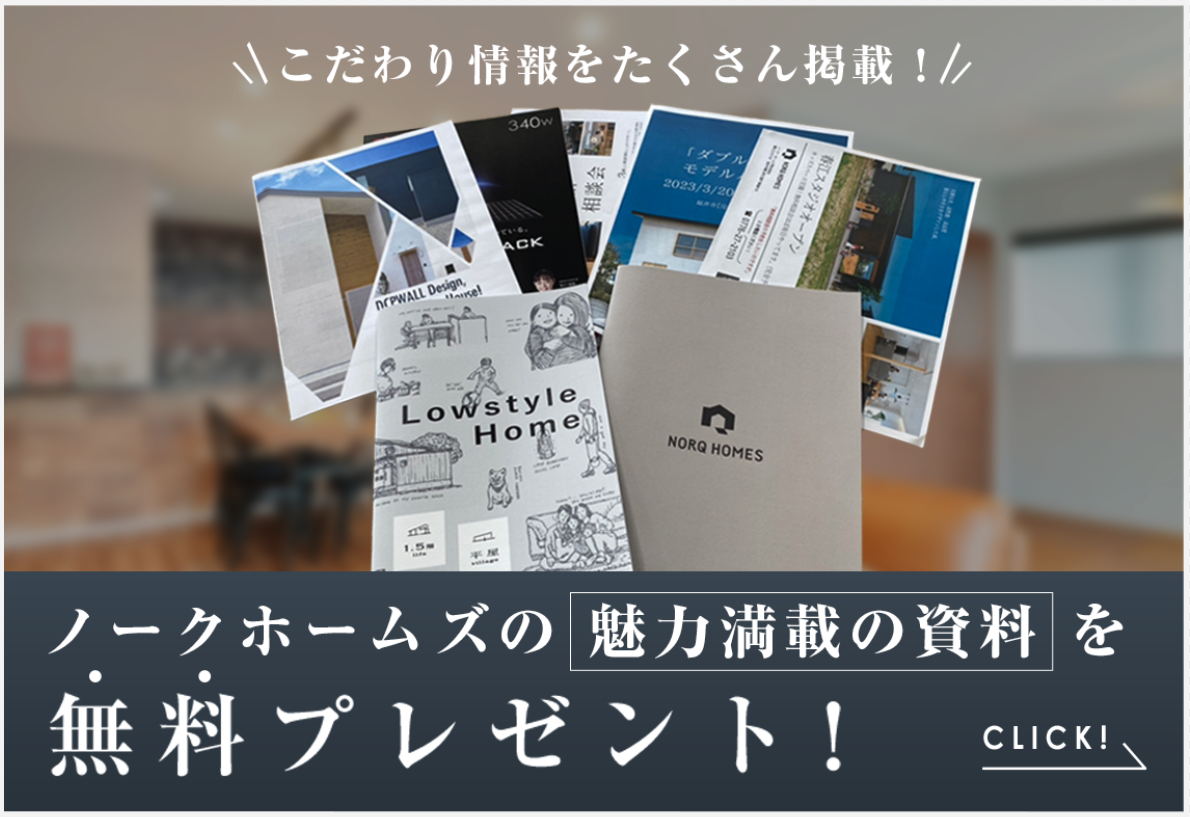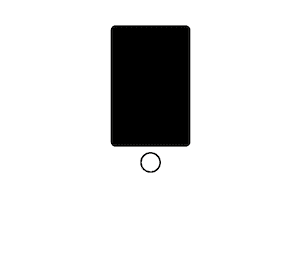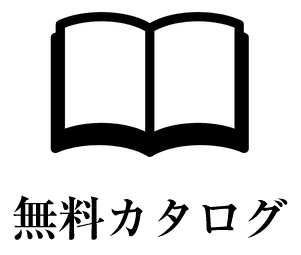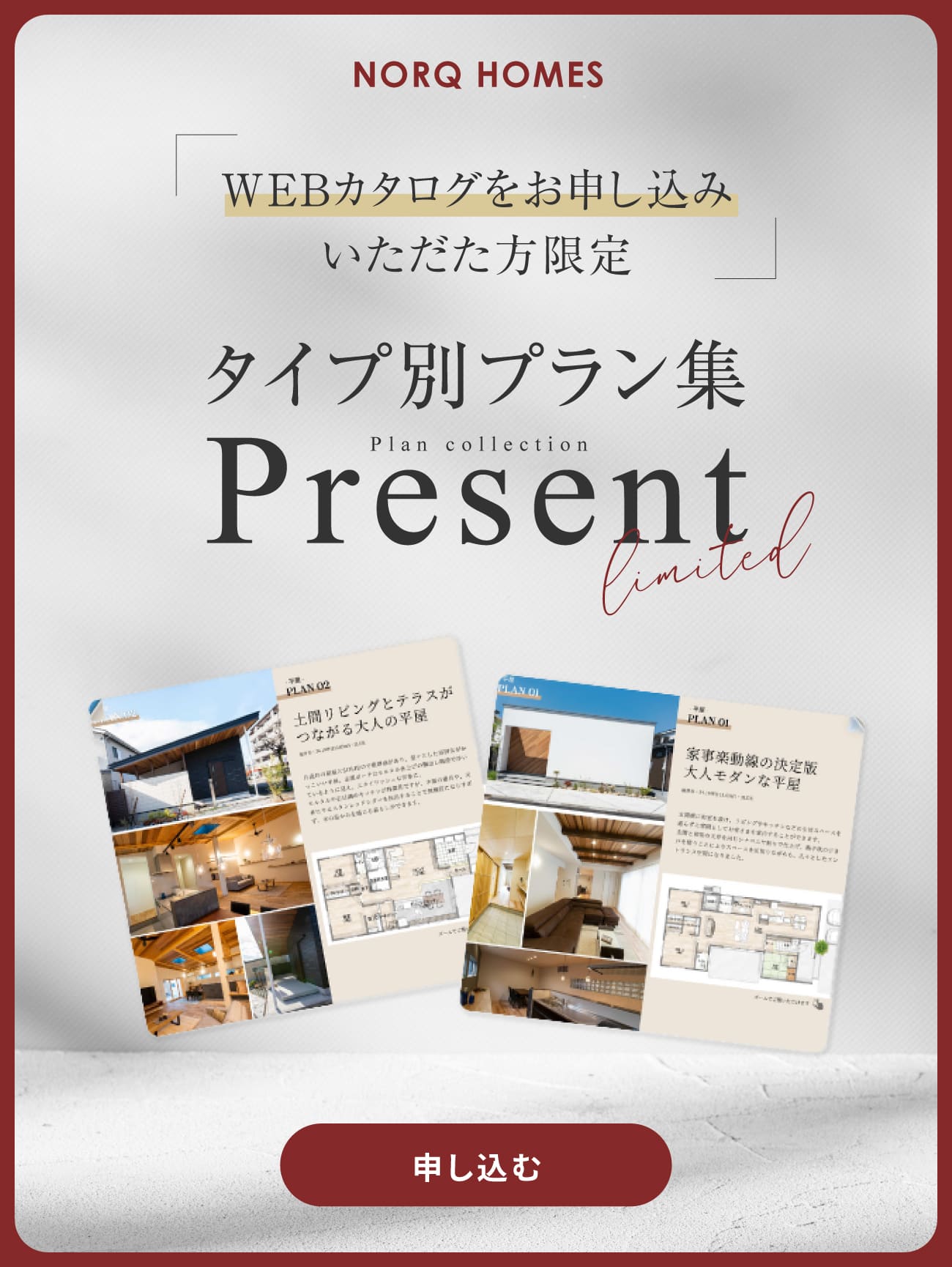断熱等級5のZEHでも寒い?等級6・7との違い、住宅の快適性と光熱費の最適バランスの見極め方

「断熱等級5の住宅でも寒いと聞いたことがある」
「北陸だと断熱等級5のZEH住宅で寒さに対応できるか不安」
家を建てる際、このような不安を抱く方は少なくありません。
実際、北陸などの雪国で快適に暮らすには断熱等級5では不十分な場合があります。
そこで今回は、福井・石川を拠点に断熱等級7を標準仕様とする工務店「ノークホームズ」が、断熱等級5の限界やより快適な家づくりのポイントを解説します。
| コラムのポイント |
|---|
|

▶ノークホームズの施工事例集
※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。
目次
断熱等級とは|断熱等性能等級とZEH水準の基礎知識

断熱等級は住宅の断熱性能を評価する指標で、快適な住環境と省エネ性能に直結します。
ここでは基準や地域区分、ZEHとの関係を解説します。
断熱等級とは
断熱等級は、住宅の断熱性を1~7の7段階で評価する基準です。
数値が高いほど断熱性が高く、UA値やηAC値などの指標に基づいています。
断熱等級と地域区分の関係
日本の省エネ基準では、全国を8つの地域区分に分け、それぞれの気候に適した断熱性能を設定しています。
例えば、寒冷地の北海道は地域区分1、温暖な沖縄は地域区分8に分類されます。
このため同じ断熱等級5でも、寒冷地や地域の気象条件によっては寒い場合があるため、地域特性を考慮した性能選びが重要です。
ZEH水準と断熱等級の関係
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、省エネ性能が高い住宅として注目されていますが、その断熱基準は断熱等級5に相当します。
これは十分な性能ではない場合があり、寒冷地ではZEH水準の家でも寒いと感じる場合があります。
断熱等級5でも寒い理由を解明|家を建てる前に知っておくべき基礎知識

断熱等級5は現在の新築住宅で広く推奨される最低基準ですが、冬の寒さに対応しきれない場面も少なくありません。
これから家を建てる方にとって、断熱性能の選び方は重要です。
ここでは、断熱等級5の限界や日本の断熱基準の現状を解説し、より快適な住まいづくりのポイントを紹介します。
断熱等級5が新設された背景
断熱等級5は、カーボンニュートラルを目指す取り組みの一環として2022年に新設されました。
これにより、断熱性能の向上が求められ、ZEH水準以上の住宅を増やすことが狙いです。
こちらの記事では、断熱等級5の具体的な基準値や、必要な断熱材の厚み、サッシ・ガラスの仕様など、高断熱の家づくりに必要な技術的な情報を詳しく解説しています。
>断熱等級5の基準値とUA値を解説|高断熱の注文住宅を建てる方必見
断熱等級5の性能
断熱等級5は、室温が10℃を下回らない程度の断熱性能が確保されており、従来の等級4よりも室内の温度差が抑えられます。
ただし、寒冷地では十分でない場合があり、冷暖房効率や快適性に課題が残るケースもあります。
世界保健機関(WHO)は室温18℃が健康に暮らせる最低水準と勧告していますので、断熱等級5ではこの水準をクリアするのは十分ではないことがわかります。
断熱等級5の体感温度と住み心地
断熱等級5の住宅では、冷暖房を使用している部屋は快適ですが、使用していない部屋や廊下では温度差を感じることがあります。
特に冬の寒冷地では、暖房をつけていない部屋が冷え込み、室温が10℃前後になる場合があります。
断熱等級5でも「寒い」と感じる理由
断熱等級5は、断熱等級4よりもUA値(外皮平均熱貫流率)やηAC値(平均日射熱取得率)の基準が厳しくなっていますが、寒さを完全に防げるわけではありません。
特に北陸など寒冷地では、断熱等級5でも冬の寒さに対応しきれないケースが見られます。
断熱等級5が最低基準となる今後の住宅事情
2030年からすべての新築住宅に対して、断熱等級5が最低限の基準として義務化される予定です。
そのため、これから家を建てる方にとって、断熱等級5以上が最低ラインです。より高い断熱性能を満たすことが将来の快適性と光熱費削減に直結する重要なポイントになります。
日本と欧米の断熱基準の違いがもたらす寒さの原因
日本の住宅は、歴史的に「夏を快適に過ごす」ことを基準に設計されてきました。
その結果、断熱性能や気密性が欧米と比べて低く、「冬は寒い」住宅が一般的です。
特に欧米では断熱性能が高く家全体の温度差が少ないため、ヒートショックによる健康被害が日本に比べて少ないのです。
福井・石川で断熱等級の選択でお悩みの方は、ノークホームズにご相談ください。
断熱等級7を標準仕様とし、北陸の厳しい寒さでも快適に過ごせる住まいづくりをご提案いたします。
※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。
断熱等級5と7の違いがもたらす寒さの快適性の差

断熱等級5と7の違いは、家の快適性や健康、光熱費に大きな影響を及ぼします。
ここでは、これから家を建てる方に向けて、断熱等級5と7の違いを解説します。
断熱等級7がもたらす高い快適性
断熱等級7は、断熱等級4と比較して冷暖房エネルギーの消費量を40%削減可能で、家全体の温度を一定に保てます。
- 温度の均一性:部屋ごとの温度差がほとんどなく、冬でも快適です。
- 薄着で過ごせる環境:高断熱・高気密により、寒さが厳しい日でもエアコン暖房だけで快適で過ごせます。
- 経済的メリット:冷暖房費を抑え、家計への負担を軽減します。
断熱等級7の住宅は快適性と経済性に優れ、寒冷地でその効果が大きく発揮されます。
室内温度差による健康への影響
断熱性能が高いと室内の温度差が少なくなり、健康面でのメリットがあります。
特にヒートショックのリスク軽減には、断熱等級7の家が有効です。
- 断熱等級5:室温が10℃程度まで下がることがあり、浴室やトイレでの寒さで体調を崩す可能性があります。
- 断熱等級7:室温が15℃未満になることはほとんどなく、ヒートショックのリスクを軽減します。
断熱等級7の家は、高齢者や小さなお子様がいるご家庭にとって安心です。
高気密・高断熱住宅であっても、設計や施工、使い方によっては期待通りの効果が得られない場合があります。
こちらのコラムでは、寒さの原因と対策について詳しく解説しています。
>高気密・高断熱住宅なのに寒い原因とは|寒い住宅を新築しないために必要な対策も紹介
断熱等級5・6・7のメリット・デメリットを徹底比較

断熱等級が違えば、メリット・デメリットも異なります。
ここでは、断熱等級5・6・7のメリットとデメリットを比較します。
断熱等級5のメリット|比較的コストがかからない
断熱等級5は、比較的安価な製品の設置でも達成可能な基準であり、一般・温暖地ではコストメリットが得やすい点が魅力です。
具体的なメリットは以下の通りです。
- 比較的コストがかからない:一般的な断熱材や設備でも達成可能なため、建築費用を抑えやすいです。
断熱等級6のメリット|温暖な地域での費用対効果に優れる
断熱等級6は、一般地の場合、快適性と省エネ性能を兼ね備えたバランスの良い選択肢です。
具体的なメリットは以下の通りです。
- 快適な室内環境:無暖房でも室温13℃を下回ることが少ないです。
- 費用対効果が高い:十分な断熱性能を備えており、快適性とコストのバランスが取れています。
- 健康的で長持ちする住まい:結露が起きにくいため、カビやダニを防ぎ、家と住む人の健康を守ります。
- 補助金の活用:断熱等級6以上が基準の子育てグリーン住宅支援事業などの補助金が活用できる
断熱等級7のメリット|快適性が高く冷暖房効率や費用対効果に優れる
断熱等級7は、寒冷地や雪国でも快適性が高く費用対効果に優れ、冷暖房効率が最も高く快適な室内環境を実現します。
断熱等級7のメリットは次の通りです。
- 全室で温度差が少ない:家全体で温度が均一に保たれ、冬でも15℃未満になることはほとんどありません。
- 健康リスクの軽減:ヒートショックなどのリスクを減らし、特に高齢者や小さなお子様にとって安心です。
- 長期的な光熱費削減:冷暖房効率が良いため、等級6よりも光熱費を抑えられます。
- 補助金の活用:断熱等級6以上が基準の子育てグリーン住宅支援事業などの補助金が活用できる
断熱等級5・6・7のデメリット比較
断熱等級5と7にはメリットがありますが、それぞれデメリットも存在します。
| 断熱等級 | デメリット |
|---|---|
| 断熱等級5 |
|
| 断熱等級6・7 |
|
世界保健機関(WHO)は冬でも室内温度18度以上を強く推奨(最低水準として報告)していますので、世界基準でみれば断熱等級7でもかならずしも十分とは言えない水準です。
出典:国土交通省「住まいと健康に関するガイドライン」
快適性と光熱費の削減効果が最も高い断熱等級7の家づくりを検討されている方は、以下の記事でメリット・デメリットを詳しく解説していますので、ぜひあわせてごらんください。
>断熱等級7・UA値とは|断熱等級7・6どちらを選ぶべきか、仕様・省エネ性能の違いなど解説
>断熱等級7の家を建てるメリット・デメリット|ハウスメーカー選びのポイントも
寒い冬に対応するための断熱等級7の効果的な工法と技術

寒冷地などの雪深い地域で快適に過ごすためには、断熱等級7の家が効果的です。
ここでは、福井・石川の工務店ノークホームズが取り入れている断熱工法と技術について解説し、寒さを防ぎ、省エネ効果を発揮する仕組みを紹介します。
ダブル断熱工法で高断熱を実現
断熱等級7を実現するための工法が、外張断熱と充填断熱を組み合わせた「ダブル断熱工法」です。
外張断熱は建物全体を外から包み、外気を遮断します。
一方、充填断熱は柱の間に断熱材を入れ、室内の熱を逃がしません。
これにより、高い断熱性と費用を抑える経済性を両立しています。
トリプルガラスと樹脂サッシで窓の断熱強化
家の断熱性能には窓が大きな影響を与えます。
ノークホームズではトリプルガラスと樹脂サッシを標準装備し、窓からの熱損失を抑えています。
トリプルガラスは冬場の冷気を遮断し、金属より熱伝導率が低い樹脂サッシで冷暖房効率を高め、窓からの熱の出入りを最小限に抑えることが可能です。
効率的な換気システム
断熱性能を最大限に引き出すには、適切な換気が重要です。
ノークホームズでは、低コストで導入可能な第一種換気システムで新鮮な空気を取り込みながら効率的に室温を保ちます。
これにより、エネルギー消費を抑えつつ快適な空気環境を維持します。
断熱等級に関するよくあるご質問

ここでは、断熱等級に関するよくあるご質問にお答えします。
断熱等級5で十分なの? どれくらいの性能?
断熱等級5は、2030年以降の新築住宅に求められる最低基準ですが、地域によっては十分な性能を発揮します。
冬場の室温が10℃を下回らない程度の性能ですが、世界的に見ると欧米などとの比較では低い水準ですので、寒冷地や快適性を重視する方にはより高い等級のほうが安心です。
ZEH住宅は寒い?断熱等級の水準は?
ZEH住宅はエネルギー収支をゼロにする設計が特徴ですが、断熱性能は等級5です。
寒冷地や快適性を求める場合、断熱等級6以上の採用が望ましく、ZEHの付加価値を最大限引き出すには他設備とのバランスが重要です。
福井・石川で高断熱住宅をお考えの方は、ノークホームズへお問い合わせください。
ダブル断熱工法とトリプルガラスで、真冬でも家中どこでも快適な住まいを実現いたします。
※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。
まとめ
これから家を建てる方にとって、断熱性能の選び方は将来の快適性とランニングコストを左右する重要なポイントです。
断熱等級5は、比較的温暖な地域以外では十分な快適性を得られない可能性があります。
特に寒冷地や雪国では快適性と光熱費の削減効果の高い断熱等級7にすることで、家中どこでも快適な温度を保ち、健康的な暮らしを実現できます。
2030年の断熱等級5の義務化、世界水準の断熱等級6~7があたりまえになる時代の家づくりの参考にしていただけると幸いです。