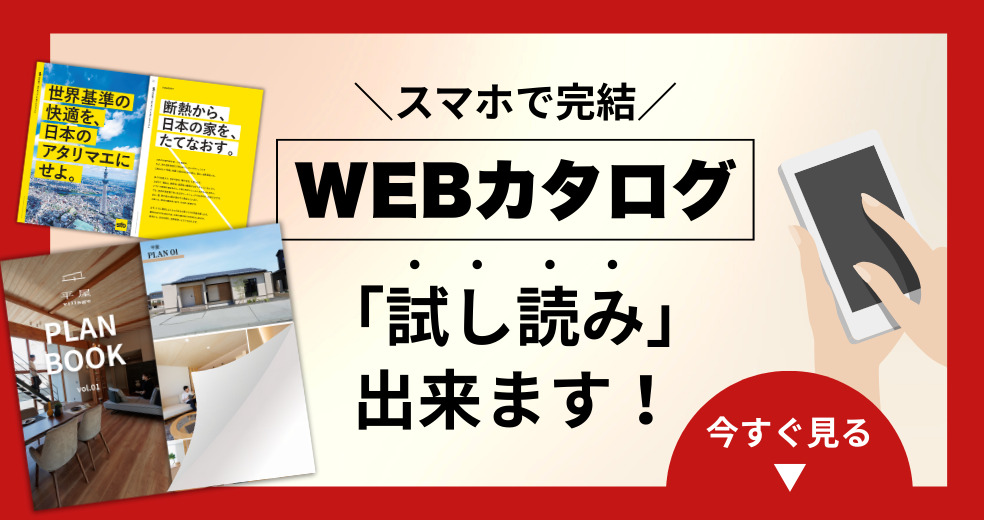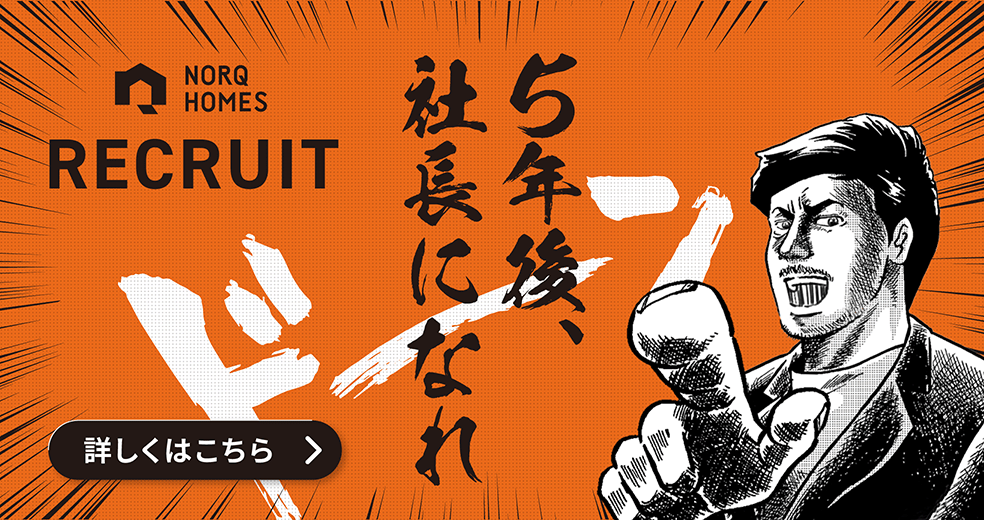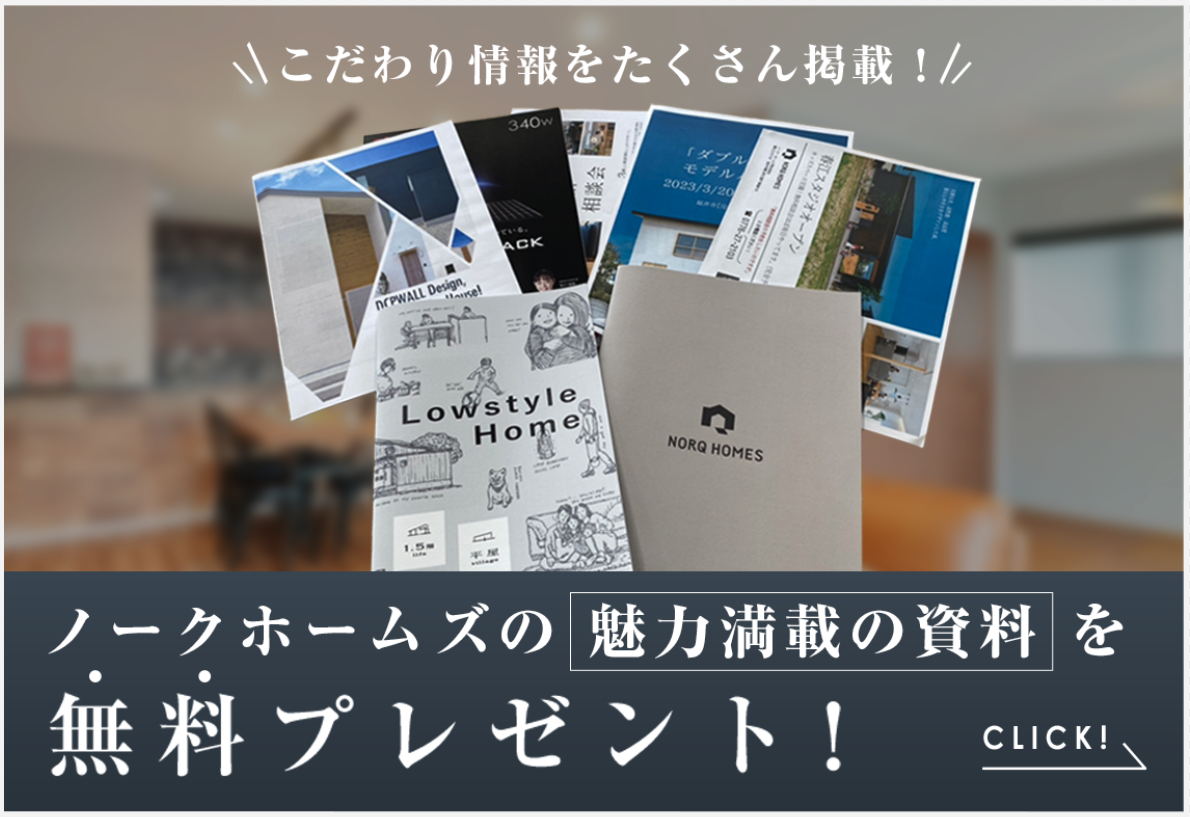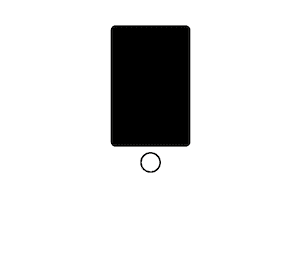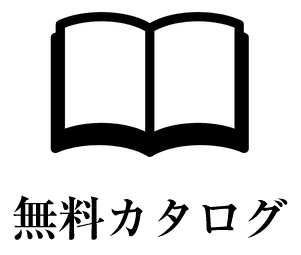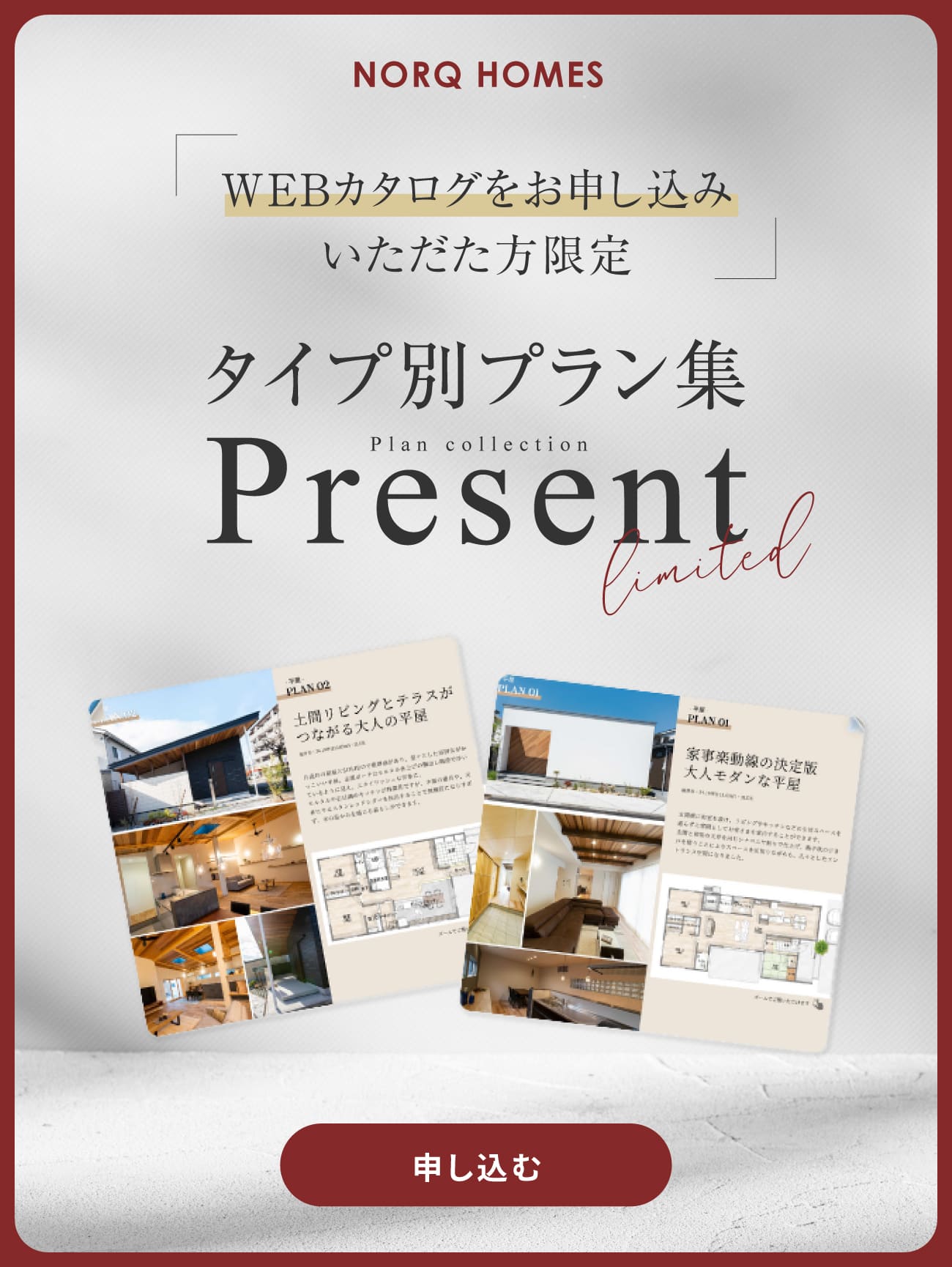建て替えできない土地・再建築不可物件とは|リフォームはできるのか、対処法をわかりやすく解説

建て替えできない土地にある家は再建築不可物件となり、解体して新築住宅を建てることが許されません。
また、2025年4月施工の建築基準法改正により、建物の増改築についても制限が増えました。
そのため、「両親が所有していた家を建て替えたい」「古家付きの土地を買って大規模なリフォームをしたい」と検討されている場合、工事ができない場合があります。
そこで今回は、福井の注文住宅工務店『ノークホームズ』が、建て替えできない土地の条件は何か、再建築不可物件の場合の対処法などを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
| コラムのポイント |
|---|
|

▶ノークホームズの施工事例集
※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。
建て替えできない土地とは

建て替えできない土地とは、建築物を解体後、新たに建物を建てることができない土地です。
詳しい条件については後ほどご説明しますが、建築基準法第43条に基づく「接道義務」に反している土地の場合、建て替えできない土地と判断されます。
建て替えできない土地が生まれた背景
建て替えできない土地が生まれた背景には、過去の無秩序な市街地形成と、新たら法律の制定が影響しています。
住宅需要の高まりと無秩序な市街地形成
戦前から戦後にかけて、都市部を中心に住宅需要が高まったことを理由に、狭い路地や袋小路には「密集市街地」が形成されていきます。
この時代は建築規制が整っていなかったため、道路幅や接道条件による制約もなく、住宅が建てることができました。
建築基準法の制定と接道義務の導入
無秩序に市街地形成がされていきましたが、安全性や防災面を考慮し、1950年(昭和25年)には「建築基準法」が制定されます。
建築基準法では、災害時の避難路や消防車・救急車の進入路確保を目的に、これまでになかった接道義務についてのルールが明確に定められました。
法改正による規制強化
建築基準法が制定された当初は、接道義務に関する規定がされたものの、すべての土地に課されていたわけではありませんでした。
しかし、昭和43年(1968年)の「都市計画法」施行、昭和46年(1971年)の建築基準法改正などにより規制は厳格化されていきます。
その結果、狭小地や密集地の多くは建て替えできない土地となり、その土地に建つ物件に関しては再建築不可物件となりました。
建て替えできる土地・できない土地を左右する接道義務とは何か
接道義務とは、幅員4メートルの建築基準法上の道路に、建物を建てる土地が2メートル以上接している必要があるというルールです。
奥まった土地の場合、道路に面する通路の間口が2メートル以上なければなりません。
ちなみに、建築基準法上の道路とは以下の通りです。
| 種類 | 概要 |
|
建築基準法42条1項1号道路 |
道路法による道路(国道・県道・都道などの公道) |
| 建築基準法42条1項2号道路 | 都市計画法や土地区画整理法等の法律により造られた道路 |
| 建築基準法42条1項3号道路 | 建築基準法の施行時の昭和25年11月23日以前から存在する道路 |
| 建築基準法42条1項4号道路 | 道路法、都市計画法などの法律により2年以内に新設、あるいは事業計画に変更がある特定行政庁が指定した道路 |
| 建築基準法42条1項5号道路 | 土地の所有者が建物を建てるために一定の基準で造られており、特定行政庁がその位置を指定した道路 |
| 建築基準法42条2項道路 | 建築基準法が施行される前から存在、あるいは都市計画区域に指定された時点で既に建築物があり、幅員4メートル未満であるものの、特定行政庁が指定した道路 |
接道義務を満たしているか確認する際は、上記の道路であれば公道・私道は問いません。
接道義務の例外
接道義務は、みなし道路・位置指定道路・43条但し書き道路・都市計画区域外のいずれかに該当する場合は例外となります。
みなし道路
みなし道路とは、建築基準法42条2項道路を指します。
建築基準法が制定される前より存在していた道路、あるいは都市計画区域に指定された際にすでに建物が建ち並んでいた場合にみなし道路とされ、道路の幅が4メートル未満であっても建築可能です。
しかし、建築可能とするには、土地と道路の境界線を後退させる工事(セットバック)を行い、幅員4メートル以上を確保する必要があります。
位置指定道路
位置指定道路は、建築基準法42条1項5号道路に該当します。
建物を建てる際に接道義務を果たすために造られ、特定行政庁より道路の位置指定を受けた私道です。
位置指定を受けるためには、次の通りいくつかの条件があります。
- 幅員4メートル以上で両側にすみ切りがある
- 排水に必要な設備を設ける
- 砂利敷やアスファルト舗装などぬかるみとならない構造にする
- 原則として通り抜け道路であり、行き止まり道路の場合には長さが35メートルより短い など
具体例としては、土地を分譲する場合などによく見られるケースです。
43条但し書き道路
43条但し書き道路とは、接道義務を果たしていないものの、建築審査会の許可を得て建築可能とされている道路です。
建築基準法施行規則第10条の3第4項では、43条但し書き道路として次の条件が定められています。
- その敷地の周辺に公園・緑地・広場などの広い土地がある
- その敷地が農道、あるいは類する公共の道に2メートル以上接する
- その敷地が避難および通行の安全な通路、道路に通づるものに接する
接道義務を満たしておらず、建物の建て替えができない土地の救済を目的に設けられた道路です。
都市計画区域外
接道義務は、都市計画区域・準都市計画区域内でのみ適用されます。
そのため、過疎地や農山村部などの区域外で建築する場合、接道義務を果たさずとも建築可能です。
土地選びの優先順位を知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。
>土地選びの優先順位を解説|土地選びのポイントチェックリスト、買わないほうがいい土地の条件も紹介
ノークホームズでは、ご希望の条件をもとにお客様の土地探しをお手伝いしています。
福井で家づくりを検討されている方はお気軽にご相談ください。
※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。
建て替えできない土地にある再建築不可物件はどうするか

接道義務を果たしていない場合、消防車・救急車などの緊急車両が進入できない、災害時に避難経路が確保できない、住宅地としての適格性がないと判断されることから、その土地に建つ建物は再建築不可物件となります。
2025年4月の建築基準法改正の影響を受け、再建築不可物件への対処法は大きく変わったため注意が必要です。
再建築不可物件はリフォームも制限あり
再建築不可物件は、リフォームであれば対応できる場合があります。
しかし、建築確認申請が不要な工事に限られるため注意しましょう。
建築確認申請とは、建築基準法に建築物が適合しているかどうかを確認する審査です。
再建築不可物件は接道義務を満たしておらず、建築基準法に適合していません。
そのため、建築確認申請の承認が下りないことから、多くのリフォームやリノベーションなどは実施不可能です。
2025年4月の建築基準法改正による変化
これまで、木造2階建ておよび延床面積200平米を超える木造平屋の場合、建築確認申請を省略できる特例とされていました。
そのため、仮に再建築不可物件であっても、特例に該当する場合は大規模リフォームも可能とされていたのです。
しかし、2025年4月の建築基準法改正によって、木造2階建ておよび延床面積200平米を超える木造平屋も特例から除外となり、「新2号建築物」に分類されることとなりました。
新2号建築物はすべての建物で建築確認申請が必要となるため、改正以前のような大規模リフォームは行えません。
新2号建築物に該当する再建築不可物件をリフォームする場合、水回りの設備交換、内装の張り替えなどの小規模リフォーム以外は難しいため注意しましょう。
再建築不可物件を建て替えるためにはどうするか
「再建築不可物件をどうしても建て替えたい」という場合、接道義務を満たさなければなりません。
接道義務を満たすための方法としては、次の6つの方法があげられます。
| 方法 | 概要 |
|
セットバックをする
|
敷地を後退(セットバック)させて道路幅を確保する |
|
位置指定道路を申請する
|
私道を新たに造るあるいは既存の私道を拡張し、行政に「位置指定道路」として申請する |
|
43条但し書き申請をする
|
周囲に広い土地がある場合、建築審査会の許可を得て例外的に建て替えを承認してもらう |
|
隣地の一部を買い取る
|
隣地の土地を購入することで間口を2メートル以上確保する |
|
隣地の一部を借りる
|
隣地の所有者と賃貸借契約を結び、借地権によって接道義務を果たす |
|
所有する土地と隣地の一部を等価交換する
|
旗竿地(※)の場合、所有する土地と隣地の一部を等価交換することで、接道部分を確保する |
※道路に接している出入り口部分が狭く、その奥により広い敷地がある土地のこと
しかし、どの方法も簡単に行えるものではないため、無理に接道義務を満たすことはおすすめできません。
時間や手間、コストがかかることを考慮し、どう対処するか慎重に判断しましょう。
実家の建て替えの流れと費用はこちらの記事で詳しく解説しています。
>【実家を建て替え】流れと費用を抑える5つのポイントを解説|福井で家を建て替えるハウスメーカー・工務店の選び方
>実家の建て替えで後悔した8つの理由と対策方法|費用、税金対策、間取りのポイントなど解説
建て替えできない土地か・再建築不可物件か確認する方法
古家付きの土地を購入・相続する前に、建て替えできる土地なのか、再建築不可物件かどうか確認したい場合には、物件の所在地を管轄する自治体に問い合わせましょう。
登記事項証明書・公図・地積測量図・建物図面などの必要書類を窓口に持参すれば、建て替えできない土地かどうかを確認してもらうことができます。
すでに施工を依頼する工務店やローカルハウスメーカーなどが決まっている場合は、該当の土地について相談してみることもおすすめです。
ノークホームズは、土地探しからワンストップでサポートできる工務店です。
>土地探しからのお客様へ
家を建てる土地選びでお困りの方は、こちらもご覧ください。
>家を建てる場所の決め方7つのポイント|土地選びのポイント、後悔しないための注意点も解説
まとめ
接道条件を満たしておらず、建て替えできない土地の場合、再建築だけでなくリフォームに関しても制限されます。
そのため、古家付きの土地を購入、あるいは相続しようと検討されている場合は、慎重に判断しなければなりません。
土地の取得や家づくりについてお悩みがある場合は、土地探しからサポートできる工務店に相談しましょう。
※建築予定地が施工エリア内(福井・石川)の方のみ対応させていただきます。